【建築名】都市はツリーではない
過去問
問題
クリストファー・アレグザンダーは、「パタン・ランゲージ(A Pattern Language)」において、過去の事例から導きだされた都市や建築を形づくるための基本的な原則を示した。
正解は ○
クリストファー・アレグザンダーは、著書「都市はツリーではない」において、人々の行動が単純なツリー状ではなく、複雑なセミラチス構造であること、また、自然発生的に形成された都市空間がセミラチス構造であることを示した。さらに、著書「パタン・ランゲージ」において、その考えを普遍的なまちづくりへと発展させ、快適な環境を「パターン」として抽出し、それを「言語」(ランゲージ)として記述・共有する方法を考案した。
問題
クリストファー・アレグザンダーは、著書「パタン・ランゲージ(A Pattern Language)」(1977年)において、都市空間における人々の行動がツリー構造で説明できることを示した。
正解は ×
クリストファー・アレグザンダーは、著書「都市はツリーではない」において、人々の行動が単純なツリー状ではなく、複雑なセミラチス構造であること、また、自然発生的に形成された都市空間がセミラチス構造であることを示した。さらに、著書「パタン・ランゲージ」において、その考えを普遍的なまちづくりへと発展させ、快適な環境を「パターン」として抽出し、それを「言語」(ランゲージ)として記述・共有する方法を考案した。
実物写真

https://www.amazon.co.jp/%E5%BD%A2%E3%81%AE%E5%90%88%E6%88%90%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%83%8E%E3%83%BC%E3%83%88-%E9%83%BD%E5%B8%82%E3%81%AF%E3%83%84%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84-SD%E9%81%B8%E6%9B%B8-%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%95%E3%82%A1%E3%83%BC-%E3%82%A2%E3%83%AC%E3%82%B0%E3%82%B6%E3%83%B3%E3%83%80%E3%83%BC/dp/430605263X
覚えるためのポイント
一級建築士の学科試験対策として、以下の3つの特徴がある:
- 難問とされる実例建築について深く理解できる
- 建築の歴史的背景、設計上の特徴、建築家の意図など、多角的な視点から学べる
- 実際の建築設計や建築評価にも役立つ実践的な内容である
詳しい解説
クリストファー・アレグザンダーは、20世紀を代表する革新的な建築家・都市計画家として、建築界に多大な影響を与えた重要な人物です。オーストリア生まれのイギリス人である彼は、数学的な思考と人間中心の設計哲学を組み合わせることで、都市計画と建築理論に画期的な視点をもたらしました。彼の代表的な著書「都市はツリーではない」(A City is Not a Tree)は、1965年に発表された革新的な論文で、現代都市計画の基本的な考え方を根本から見直すきっかけとなり、世界中の都市計画家たちに新たな洞察を提供しました。
まず、「都市はツリーではない」という論文の核心部分について詳しく見ていきましょう。アレグザンダーは、従来の都市計画における最大の問題点として、都市構造を単純な階層構造(ツリー構造)として捉えようとする傾向を鋭く指摘しました。ツリー構造とは、例えば「都市→地区→近隣→街区→建物」というように、要素が枝分かれしていく単純な階層関係を指します。この考え方は、一見論理的で整然としているように見えますが、実際の都市の複雑さを十分に反映していないとアレグザンダーは考えました。
しかし、アレグザンダーの綿密な観察によれば、実際の都市における人々の活動や関係性は、そのような単純な階層構造では到底説明できないものでした。例えば、ある人が住んでいる場所、働いている場所、買い物をする場所、娯楽を楽しむ場所などは、必ずしも同じ「枝」上にあるわけではありません。むしろ、これらの活動は複雑に重なり合い、予想もしない形で相互に関連し合い、豊かな都市生活を形作っているのです。
このような観察から、アレグザンダーは、この複雑な重なり合いの構造を「セミラチス構造」と名付けました。セミラチスとは、要素同士が多様な形で重なり合い、複数の関係性を同時に持つことができる柔軟な構造を指します。例えば、カフェという一つの場所が、仕事場としても、社交の場としても、休憩所としても、時には文化的イベントの会場としても機能するように、都市の要素は複数の役割や意味を同時に持ち得るのです。この多機能性こそが、活気ある都市空間の本質的な特徴だとアレグザンダーは主張しました。
特に注目すべきは、アレグザンダーが世界中の自然発生的に形成された都市(例えば、中世ヨーロッパの商業都市や、アジアの伝統的な集落)を丹念に研究し、これらがいずれもセミラチス構造を持っていることを発見した点です。これらの都市は、何世紀にもわたる人々の実際の生活や需要に応じて有機的に発展してきたため、一見無秩序に見えても、実は非常に複雑だが豊かな関係性のネットワークを形成しているのです。この発見は、現代の都市計画に大きな示唆を与えることとなりました。
この画期的な発見を踏まえて、アレグザンダーは1977年に「パタン・ランゲージ」(A Pattern Language)を発表します。この著書は、「都市はツリーではない」で示された理論を、より実践的で具体的な方法論へと発展させた集大成とも言えるものです。パタン・ランゲージとは、快適な環境を作り出すための設計パターンを、まるで言語のように体系化し、誰もが理解し活用できる形にまとめたものです。
パタン・ランゲージの特徴的な点は、それまで建築の専門家だけが持っていた都市計画や建築設計の知識を、一般の人々にも理解し使用できる形式で提示したことです。例えば、「明るい階段」「歩道のカフェ」「中庭のある家」といった具体的なパターンを示し、それぞれのパターンがなぜ人々の生活を豊かにするのか、どのような文脈で機能するのか、そしてどのように実現できるのかを、詳細な図解と説明文で分かりやすく解説しています。
これらのパターンは、決して単独で存在するのではなく、常に相互に関連し合い、影響を与え合っています。例えば、「歩道のカフェ」というパターンは、「活気のある通り」や「人々の集まる広場」、「日陰のある歩道」といった他のパターンと有機的に組み合わさることで、より豊かで魅力的な都市空間を生み出すことができます。この相互関連性は、まさにセミラチス構造の考え方を実践的な形で反映したものと言えるでしょう。
アレグザンダーのこれらの革新的な理論は、建築や都市計画の分野に留まらず、ソフトウェア設計やユーザーインターフェースデザイン、組織設計など、実に様々な分野に大きな影響を与えています。特に、複雑なシステムを理解可能な形で記述し、共有するという方法論は、現代の様々な設計分野で広く応用されており、その影響力は今なお拡大し続けています。
このように、アレグザンダーの理論は、都市や建築を単なる物理的な構造物としてではなく、人々の生活や活動が織りなす複雑な関係性のネットワークとして捉える新しい視点を提供しました。この人間中心の考え方は、現代の持続可能な都市づくりや、環境に配慮した建築設計においても重要な指針となっており、次世代の都市計画家たちにも大きな影響を与え続けています。








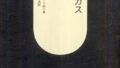

コメント