【建築名】「見えがくれする都市」
過去問
問題
「見えがくれする都市」は、芦原義信の著作で、日本の建築空間や都市空間の美しさをつくる潜在的な秩序を、美学的及び幾何学的な観点から考察した。
正解は ×
「見えがくれする都市」は、槇文彦(日本)らによる著書である。副題に「江戸から東京へ」とあるように、その著書においては、江戸の町の複雑な地形等が、現在の東京にどのように潜在しているかについて、都市全体、道、地形等の様々な視点から分析している。
なお、芦原義信の代表的な著書には「街並みの美学」があり、世界各地の街並みを比較し、都市・建築・空間について理論的に考察している。
実物写真
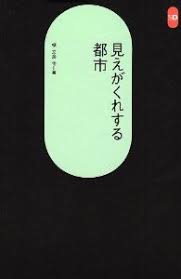
https://www.cpij.or.jp/com/gp/books_review/301books01.html
覚えるためのポイント
「見えがくれする都市」の一級建築士試験対策上の特徴は:
- 建築の歴史的背景の理解を深めることができる
- 設計上の特徴を的確に把握できる
- 多角的な視点からの分析手法を学ぶことができる
詳しい解説
「見えがくれする都市」は、プリツカー建築賞受賞者である槇文彦と研究チームによって執筆された画期的な著書です。副題の「江戸から東京へ」が示唆するように、本書は江戸の都市構造が持つ複雑な地形や空間的特質が、現代の東京の都市景観にどのように内在し、影響を与えているかについて、都市計画、道路網、地形学など、多岐にわたる視点から綿密な分析を行っています。
「見えがくれする都市」について、詳細に解説させていただきます。
1. 著者と基本情報
本書は、戦後日本を代表する建築家の一人である槇文彦と、都市計画や建築史の専門家からなる研究チームによって執筆された重要な学術的著作です。タイトルの「見えがくれする都市」に加えて、「江戸から東京へ」という副題が付けられており、これは本書が追求する都市の歴史的連続性と空間的特質を端的に表現しています。
2. 本書の主要テーマと分析視点
本書の中心的なテーマは、江戸時代から現代の東京に至るまでの都市構造の連続性と変容です。特に以下の観点から詳細な分析が行われています:
- 都市全体の構造分析
- 道路網とその特徴
- 地形的特性とその影響
3. 研究手法と特徴
本書の特筆すべき点は、以下の複合的なアプローチにあります:
- 歴史的視点:江戸から東京への都市の変遷を丹念に追跡
- 地理的視点:複雑な地形との関係性の分析
- 都市計画的視点:街路パターンや都市構造の考察
- 文化的視点:都市空間における日本的特質の探求
4. 江戸から東京への継承
本書は特に、江戸時代の都市構造が現代の東京にどのように影響を与えているかについて、詳細な分析を行っています。具体的には:
- 地形による都市形成への影響
- 街路パターンの継承と変容
- 都市の空間構造の連続性
- 場所性の継承
5. 都市空間の重層性
本書のタイトルである「見えがくれ」という概念は、日本の都市空間における以下のような特質を示唆しています:
- 空間の重層的な構造
- 視覚的な奥行きの形成
- 都市景観の連続的な変化
- 空間認識の多様性
6. 現代的意義
本書の現代的意義として、以下の点が挙げられます:
- 都市計画における歴史的文脈の重要性の提示
- 日本の都市空間の特質の理論化
- 現代都市設計への示唆
- 都市の持続可能性についての考察
7. 建築学的価値
本書は、建築教育においても重要な位置を占めており、一級建築士試験の学習教材としても活用されています。その理由として:
- 建築の歴史的背景の理解
- 設計上の特徴の把握
- 建築家の意図の解読
- 多角的な視点からの分析手法
結論
「見えがくれする都市」は、単なる都市研究書を超えて、日本の都市空間の本質を探求した記念碑的な著作といえます。江戸から東京への都市の変遷を詳細に分析することで、現代の都市計画や建築設計に革新的な視点を提供し、日本の都市空間理論の発展に多大な貢献をもたらした貴重な研究成果となっています。








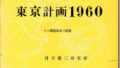

コメント