【タイトル】
「知らなきゃ崩れる!? 溶接“ショートビード”が構造を一瞬で脆くする本当の理由」
【衝撃的な結論】
“ショートビード”という短い溶接線一発で、鉄骨構造の強度と粘りが壊れ、亀裂や割れが起こるリスクが跳ね上がる。
【理由】
ビード(bead)とは、溶接でできる金属の“うねうねした盛り上がり”のこと。
このビードが極端に短いと「ショートビード」と呼ばれます。板厚6mm以上では最低でも40mm以上、6mm以下では30mm以上が基準とされています。ミカオインベスター
なぜなら、短いビードでは溶融金属が急速冷却されてしまい、焼き入れ状態になって“硬くて脆い性質”になってしまうからです。また、始端・終端部には溶け込み不良や欠陥が発生しやすく、割れや応力集中の温床になります。JWES+2合成スラブ+2
【具体例】
ある鉄骨造建築で、梁と柱の仮溶接に“長さわずか10mm”というショートビードを使ったとします。
この短さだと溶接金属が周囲の冷たい母材に急激に冷やされ、硬く脆くなり、応力や衝撃に耐えきれずひび割れが入り始めます。
また、溶接の始まり・終わりで溶け込み不足や剥離が起き、せっかくの構造が部分的に弱点化してしまいます。合成スラブ+2Sasst+2
【結論】
ショートビードは“見えない致命傷”を構造に刻む危険な選択です。
溶接設計や施工においては、ビード長さ・始端終端処理・熱管理などを徹底しなければなりません。
建築初心者もこの知識を持つことで、「この現場、これおかしくない?」と安全性を問える目を養うことができます。
もしあなたが現場で見かけた「ちょっと短すぎる溶接」や「ヒビの始まり」を経験したら、コメントで教えてください。皆で建築の安全意識を高めましょう!









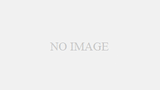
コメント