タイトル:
「コンシステンシー」が建築を壊す?あなたが知らない“流動性の罠”
【衝撃的な結論】
コンクリートの「コンシステンシー(流動性・粘度)」を誤ると、建物の耐久性や仕上がりを台無しにする――つまり、正しい“粘り”がなければ建物は壊れやすくなる。
【理由】
コンシステンシーとは、コンクリートが「どれだけドロっとしているか」という性質で、水量や材料の比率で変わる性質です。施工管理・転職の窓口|施工管理のキャリアを+1するメディア+2週刊助太刀 | ゲンバをもっと面白く+2
この性質が適切でないと、流動性が高すぎて部材同士が分離したり、逆に固すぎて隙間に入り込めず気泡や空隙が残ったりします。つまり、強度・密度・仕上がりに悪影響をもたらすのです。
【具体例】
例えばスランプ試験では、コンクリートをコーン形状の型に入れて抜いたとき、形を保てるかどうかで「スランプ値」を測ります。この値=コンシステンシーとほぼ同義で、打設しやすさや仕上がりの判定に使われます。週刊助太刀 | ゲンバをもっと面白く+1
もしスランプ値が高すぎれば、コンクリートの骨材が沈降したり、材料が分離したりする可能性が高まる。そして逆に低すぎれば、充填不良で空洞が残るリスクがあります。土木LIBRARY+1
【結論】
建築現場では「見た目だけ派手なデザイン」よりも、目に見えない“中の性質”が命綱。コンシステンシーを正しくコントロールできるかが、耐久性と品質を左右します。初心者であっても、この用語の意味と実験方法(スランプ試験など)だけは理解しておいて損はありません。
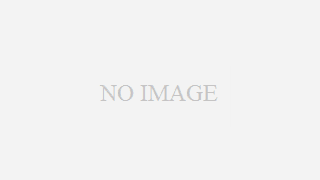

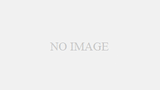
コメント