リーダーとリーダーシップの違い
リーダーシップには色々な定義があります。まず、リーダーとリーダーシップの違いは何でしょうか。
リーダーとは実際にいる人のことです。一方、リーダーシップは人と人との間で起こることです。リーダーとついていく人(フォロワー)の間にあるものです。つまり、役職や肩書きがあるだけではリーダーシップは生まれません。
リーダーが人に影響を与えるためには、周りの人から「この人について行きたい」と思われることが大切です。リーダーシップは、周りの人の信頼によって成り立っているのです。
リーダーシップと「信頼」の関係
リーダーシップの研究者J・クーゼスとB・ポスナーは、リーダーシップの本質は「人が喜んでついていくこと」だと考えました。そして、周りが喜んでついていくリーダーは「信頼できる人」だと言っています。
心理学者のE・P・ホランダーは、リーダーシップが生まれる過程を、将来リーダーになる可能性のある人とチームメンバーの間の期待関係の中に見つけました。
新しい組織に入ったばかりの人は、最初からリーダーとして見られることはあまりありません。最初はただ普通にやり方に従って仕事をすることが求められます。しかし、成果を出せるようになってリーダーになると、今までと違う新しいやり方が期待されるようになります。ホランダーはこれを「特別な行動」と呼びました。これは組織の中で新しいアイデアを出したり変化を起こしたりする行動のことです。
この考え方は「信頼貯金理論」とも呼ばれています。つまり、「この人についていけば間違いない」という信頼が貯まったら、その信頼を使って大きな変化(イノベーション)を起こすことが期待されるということです。
リーダーへの信頼が高まると、周りの人はリーダーの新しい取り組みを応援するようになります。このように、リーダーシップはリーダー一人だけでなく、周りの人も含めて作り上げていくものなのです。
リーダーに求められるもの
アメリカの調査に見る「リーダーの条件」
私たちは「あの人にはリーダーシップがある」といったことをよく言いますよね。これは、誰もが持っている「リーダーシップの素朴理論」と呼ばれるものです。
この「リーダーシップの素朴理論」(どんな人にリーダーシップを感じるか)についてアメリカで調査が行われました。1987年、1993年、2002年の3つの調査では、どの年も一番多かった言葉は「正直な」でした。2位はいつも「前向きの」で、3位と4位は「わくわくさせてくれる」と「有能な」が年によって順位が入れ替わっていました。
つまり、リーダーの一番大事な条件は「正直さ」だということです。どんなに優秀でも素晴らしい経歴があっても、正直でない人には人はついていきません。「有能な」だけではリーダーにはなれないのです。
聴衆を引きつけるプレゼンテーション力
リーダーシップの考え方には、うまく話したり人を説得したりする力が大切だと言われているものもあります。そう考えると、人前で話す力もリーダーシップの一部だと言えるでしょう。
私がこれまで上手に話す人たちに聞いてきた結果、人前で話すときのコツとしてよく聞かれたのは「動け」「問え」の2つでした。
まず「動け」について。話をするとき、同じ場所に立ったままでなく、動き回ることで人の注目を集めやすくなり、聞いている人との距離が近くなります。話す人が元気いっぱいに見える効果もあります。
次に「問え」について。一方的に話すだけでなく、聞いている人に質問することで、聞き手が前のめりになります。「ただ聞くだけ」という聞き手の退屈さをなくすこともできます。
状況に合わせて行動できる力
経験を積むほど、多くの人が自分なりの考え方を作るようになります。その中には、今までの考え方と矛盾するものもあるでしょう。そうした矛盾は悪いことではありません。その時の状況に合ったほうを選べばいいのです。
リーダーシップの研究では1960年代後半から、「効果的なリーダーシップは状況(仕事の内容、部下の成長度合い、人間関係の良さ、持っている権限の大きさなど)によって変わる」という「状況に合わせたリーダーシップ理論」が注目されました。つまり、取るべき行動は状況によって変わるという考え方が広まったのです。
例えば先ほど紹介したアメリカの調査では、ついていきたいと感じるリーダーの条件として「正直さ」が上位にありました。その一方で、リーダーは時には「演じる」ことも必要です。実際、筆者がこれまで経営者の話を聞くと、「厳しい状況の時こそ、明るく振る舞った」という人が多かったです。決まりきった考え方にこだわるのではなく、状況に合わせて柔軟に行動できる力が、リーダーシップでは大切なのです。
優れたリーダーたちの「考え方」
R・エンリコ(ペプシコ)
ペプシコの社長を務めたR・エンリコは、リーダーシップについて5つの考え方を持っていました。そしてこの考え方に基づいて、自分の経験と結びつけながら、自社の経営幹部候補に自らリーダーシップ研修を行いました。一つずつ紹介します。
1つ目の考え方は「違う視点で考えよう」です。これは、今までと同じような改善を重ねるのではなく、事業の成長を促すような、新しくて大きなアイデアを大切にすべきだということです。
2つ目は「リーダーとしての視点を持とう」です。はっきりとした視点を持つことで、チャンスを活かせます。アイデアを組織の内外の人に広く支持してもらうためにも、リーダーとして一つの視点を育てておく必要があります。
3つ目は「考えやアイデアを現場に持っていって試してみよう」です。アイデアを大きく実行する前に、小さな場でその効果を確かめるということです。具体的には、厳しい意見をくれそうな人、そのアイデアを実現する方法を知っていそうな人、行動を起こしてくれそうな人に、アイデアの内容を話してみます。
4つ目は「ビジョンにまとめよう」です。アイデアをはっきりとしたビジョンの形にします。ここには、ビジョンの達成度を測る方法を示すことや、重要な関係者から協力を得ること、反対する人への対策をあらかじめ考えておくことも含まれます。
5つ目は「実際に形にしよう」です。ビジョンを語って人々のやる気を引き出し、行動の方向性を示します。
小倉昌男(ヤマト運輸)
ヤマト運輸で社長を務めた小倉昌男さんは、「宅急便」事業を始めたリーダーです。彼は本の中で、経営リーダーの10の条件をまとめています。ここではそのうち3つを紹介します。
第1の条件は、筋道立てて考える力です。経営とは筋道を積み重ねることだからです。自分の頭で筋道立てて考えられなければ、新しいアイデアは生まれません。宅配事業を始める時も、周りから反対されましたが、筋道立てて反論できたからこそうまくいきました。
時代の流れを読む力も大切だとされています。経営は社会の変化に影響されるものだからです。宅急便を始めたのは1976年で、オイルショック後の厳しい時期でした。それでも事業がうまくいき、5年後には利益が出るようになったのも、時代が味方したからだと考えています。
また、長い目で見て優先順位をつけて経営する「戦略的な考え方」も条件に挙げています。サービス第一、利益第一など、大切なことをすべて優先するのではうまくいきません。宅配事業では、利益よりもサービスを重視することで、長期的に費用を回収でき、成功につながりました。
自分なりのリーダーシップをつくる
考え方と経験をつなげる
この本は、自分でリーダーシップの考え方を作り、それを実践するための案内書です。本を読んだら、ぜひ考え方を作って実践してみてください。
自分の考え方づくりは、まずは簡単なコツを言葉にすることから始めましょう。人に動いてもらう方法について、誰でも自分なりの考えを持っているものです。リーダーシップで大切だと思うことを、当たり前のことでも、人に笑われそうでも、勇気を出して書き出してみましょう。そうして生まれた言葉について周りに意見を聞いたり、リーダーシップが上手な人を見たりして、経験を積み重ねて良くしていきます。こうした取り組みを続けるうちに、リーダーシップに関する自分の考え方が形になっていくでしょう。









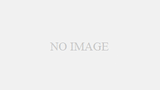
コメント