題名:茶室
過去問・類似問題
問題1 計画 R05-02改
妙喜庵待庵(京都府大山崎町)は、二畳隅炉に次の間をもつ、16世紀末頃に建て
られたと推定されている、利休好みの草庵風茶室である。
問題1 正
問題2 計画 H27-02
孤篷庵忘筌(京都市)は、17世紀に小堀遠州によって造立された、縁先にわたし
た中敷居の上の障子とその下の開口が特徴的な書院風茶室である。
問題2 正
問題3 計画 H27-02改
密庵(京都市)は、小堀遠州の好みと伝えられる四畳半台目のやや書院風の茶室
であり、床の間が二つあるのが特徴である。
問題3 正
問題4 計画 H27-02
如庵(愛知県犬山市)は、17世紀にもと建仁寺内に造立された、大小五つの窓や
躙口の配置が特徴的な茶室である。
問題4 正
問題5 計画 H27-02改
笑意軒(京都市)は、17世紀に桂離宮の敷地南端に造立された、茅葺寄棟屋根や
深い土庇等の農家風の外観をもつ格式にこだわらない自由な造形の茶室である。
問題5 正
覚え方・解説
■妙喜庵待庵(みょうきあん たいあん) 【国宝3茶室】
・千利休 作(商人茶人)
・草庵茶室(草ぶき)← わび・さび
■孤蓬庵忘筌(こほうあん ぼうせん)
・小堀遠州 作(武家茶人)
・書院茶室(武家の格式をもった端正な茶室)←「綺麗さび」と言われる。
■密庵(みったん) 【国宝3茶室】
・小堀遠州 作(武家茶人)
・やや書院風の茶室で、床の間が二つあるのが特徴(文化庁の表現)
■如庵(じょあん) 【国宝3茶室】
・織田有楽斎 作(織田信長の弟)
・大小五つの窓や躙口の配置が特徴(五つは多い!)
覚え方 ■「こ蓬庵忘筌」は「こ堀遠州」。「こ」つながりで覚えましょう!
■孤蓬庵忘筌も密庵も小堀遠州作で、大徳寺内にあります。









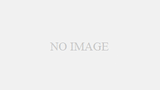
コメント