題名:木材の積雪時以外の許容応力度
過去問・類似問題
問題1 構造 H25-27
木材の繊維方向の短期許容応力度は、積雪時の構造計算をする場合を除いて、準強度の2/3である。
問題1 正。問題1は、短期が基準強度の何倍か
問題2 構造 H16-22
木材の繊維方向の短期許容応力度は、積雪時の構造計算以外の場合、長期許容応力度の2/1.1倍とされている。
問題2 正。問題2は、短期が長期の何倍か
問題3 構造 H20-23
木材の繊維方向の長期許容応力度は、積雪時の構造計算以外の場合、木材の繊維方向の基準強度の1.1/3倍の数値とする。
問題3 正。問題3は、長期が基準強度の何倍か
覚え方・解説
・まずは基本事項を3つ理解してください。
1.許容応力度とは
・許容応力度とは、部材に生じる応力度(力/断面積)について、安全に余裕を見て許容できる限界値をいいます。
応力度 ≦ 許容応力度
・左辺の応力度は「かかる力」、右辺の許容応力度は「耐える力」と考えることができます。
・許容応力度には、短期と長期があります。
2.短期許容応力度と長期許容応力度はどっちが大きい?
・ズバリ「短期」のほうが大きいです。
・一般に短期は10分程度、長期は50年程度を想定しています。
■短期許容応力度 → 10分間ならその力が働いても大丈夫という限界値
■長期許容応力度 → 50年間その力が働いても大丈夫という限界値
短期許容応力度 > 長期許容応力度
・短い時間だったら頑張って大きな力にも耐えられますが、同じ力が長い時間かかると、へたばってしまうわけです。
3.許容応力度と基準強度Fの関係
・「基準強度F」とは、上記の許容応力度や下記の材料強度を定めるための基準となる強度で、具体的な値は告示で定められます。
【例】・異形鉄筋SD345 → F =345N/㎟
・鋼材SN400B → F =235N/㎟(板厚40 ㎜以下)
・許容応力度には、長期許容応力度と短期許容応力度があり、さらに、それぞれに圧縮、引張、曲げ、せん断などがあります。
・それらを一つずつバラバラに決めなくても、基準となる強度を一つ定めて
「基準強度F」と呼び、それぞれの許容応力度はその何倍かで表すのです。
【例】① 鋼材の長期許容圧縮応力度は、基準強度F の2/3
② 木材の繊維方向の短期許容応力度(積雪時以外)は、基準強度Fの2/3 など
③ コンクリートの長期許容圧縮応力度は、設計基準強度Fcの1/3
<③の補足>
・コンクリートでは「基準強度F」と呼ばずに「設計基準強度Fc」と呼びます。
・コンクリートは、鉄骨等のように最初から強度が分かっている材料があるわけではありません。したがって、設計者が先に例えば24N/㎟の強度があると定めて設計をした後、施工者がその強度を確保するように調合し、施工管理します。コンクリートにおいて、この設計に用いた強度を「設計基準強度Fc」と呼びます。
4.材料強度とは
・部材の終局強度(=終局耐力=保有水平耐力)を算定するために用いる材料の強度です。ほとんどの場合は、基準強度Fの値そのものです。
・コンクリートと木材は、長期荷重時のクリープ現象があるため、長期許容応力度が低めに設定されています。









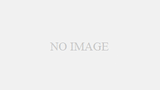
コメント