題名:層間変形角
過去問・類似問題
問題1 構造 H18-21 高さ20m、鉄骨造、地上5階建ての建築物の場合、層間変形角が1/200以下であることの確認及び保有水平耐力が必要保有水平耐力以上であることの確認を行った。
問題1 正。
設問の「高さ20m、鉄骨造、地上5階建ての建築物」は、耐震計算ルート2以上、すなわち許容応力度等計算以上としなければなりません。したがって、上位の保有水平耐力計算は可です。層間変形角は、表の「原則」の値である「1/200以内」とします。
問題2 構造 H23-26 層間変形角の確認において、構造耐力上主要な部分の変形によって建築物の部分に著しい損傷が生じるおそれのない場合には、層間変形角の制限値を1/120まで緩和できる。
問題2 正
問題3 構造 H22-26 一次設計用地震力によって生じる各階の層間変形角が1/180となったので、別途に、帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれがないことを確認した。
問題3 正
↑3つの論点は同じです。原則として層間変形角は1/200以内ですが、帳壁(ALC版などのカーテンウォール)、内外装材、設備等に著しい損傷の生じるおそれがない場合には、1/120までは可です。
問題4 構造 H04-16 鉄骨造の建築物において、外壁のALC版を変形に追従できるようにし、層間変形角を1/150以内で設計した。
問題4 正
問題5 法規 H20-02 主要構造部を準耐火構造とした建築物の地上部分の層間変形角は、原則として、1/150以内でなければならない。
問題5 正。
法規の出題です。建築基準法施行令109条の2の2。これは、構造強 度上というより、防火上の規定です。すなわち、地震時に火炎が通る亀 裂等の損傷及び隙間を生じないための規定です。
覚え方・解説
・層間変形角とは、各階に生じる水平方向の層間変位を、その階の高さで除した値です。
層間変形角 →原則 1/200 以内
帳壁、内外装材、設備等に著しい損傷のおそれがない場合→ 1/120 以内
主要構造部が準耐火構造等 →1/150 以内
・「帳壁に著しい損傷のおそれがない場合」の代表例は、カーテンウォールのロッキング工法(回転)です。









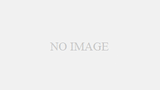
コメント