題名:主筋量、せん断補強筋量と靱性、脆性
過去問・類似問題
問題1 構造 H30-14
鉄筋コンクリート構造の保有水平耐力計算において、柱の塑性変形能力を確保す
るため、引張鉄筋比を大きくした。
問題1 誤。
問題2 構造 H22-11
鉄筋コンクリート構造において、一般に、柱部材の引張鉄筋が多いほど、曲げ耐
力は大きくなり、靭性能は向上する。
問題2 誤
問題3 構造 H23-26
鉄筋コンクリート造の柱は、せん断補強筋量が規定値を満足する場合、主筋が多
く入っているほど変形能力が大きい。
問題3 誤
・いずれも同じ内容です。主筋(引張鉄筋)が多いほど、曲げ耐力が大きくなり
ます。それにより曲げ降伏よりもせん断破壊が先行するため、靱性は低下しま
す(=変形能力は低下します)。
覚え方・解説
・RC造において、
■曲げモーメントは、主筋が負担します。
■せん断力は、柱では帯筋(せん断補強筋)が負担します。
・これは次のように言い換えることもできます。
■主筋を多くすると、曲げ強度(耐力)が大きくなる。
■帯筋を多くすると、せん断強度(耐力)が大きくなる。
・柱の柱頭部に水平力が作用した場合、柱脚部分には曲げ応力度とせん断応力度が同時に生じます。
・水平力が大きくなるにつれて、曲げ応力度とせん断応力度は、ともに大きくなっていきます。
■先に曲げ強度に達したときは、縁から曲げ降伏が始まります。すぐ曲げ破壊には至らないので「曲げ降伏」と言います。
・これは靱性の高い破壊形式です。
・なぜなら、縁が曲げ降伏した後も、降伏が断面の中心部まで進行し、全断面が降伏して全塑性状態になるまで粘り強く耐えられるからです。それを「靱性が高い」「変形能力が高い」と言います。
■先にせん断強度に達したときは、せん断破壊します。
・これは脆性破壊です。急激に耐力が低下します。降伏とほぼ同時に破壊しますので、「せん断破壊」と言います。
■主筋を増やすと
曲げ強度が大きくなり、曲げ降伏よりも先にせん断破壊してしまいます。脆性破壊です。
■帯筋(せん断補強筋)を増やすと
せん断強度が大きくなり、せん断破壊よりも曲げ降伏が先行し、全断面が降伏して全塑性状態になるまで粘り強く耐え、靱性が確保されます。









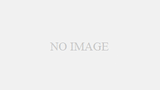
コメント