題名:SN材
過去問・類似問題
問題1 構造 R01-29
建築構造用圧延鋼材(SN材)C種は、B種の規定に加えて板厚方向の絞り値の下限が定められており、溶接加工時を含め板厚方向に大きな引張力が作用する角形鋼管柱の通しダイアフラム等に用いられている。
問題1 正。
問題2 構造 H25-29
建築構造用圧延鋼材(SN材)には、A、B、Cの三つの鋼種があるが、いずれもシャルピー吸収エネルギーの規定値がある。
問題2 誤。シャルピー衝撃試験は、切欠きの入った試験片にハンマーで衝撃を与え、破断するのに要する吸収エネルギーを求める試験で、吸収エネルギーが大きいと、塑性変形能力が大きいと言えます。塑性変形能力が求められているのは、B種とC種だけで、A種には求められていません。したがって、シャルピー吸収エネルギーの規定値があるのは、B種とC種だけです。
問題3 構造 H19-20
プレス成形角形鋼管(BCP材)は、冷間加工を行う原材の材質がSN材のB種又はC種に準拠している。
問題3 正。冷間成形角形鋼管(BCP:ボックスコラムプレス/BCR:ボックスコラムロール)は、SN材のB種又はC種の鋼板を成形したものです。
覚え方・解説
さっそくSN材(建築構造用圧延鋼材)のポイントを確認しましょう。
鋼種 特徴と使用箇所 具体的な
使用箇所 降伏点の規定
SN400A:降伏点の下限値だけが定められている。
SN400B:降伏点の下限値だけでなく、上限値も定められている。
SN400C:降伏点の下限値だけでなく、上限値も定められている。
■降伏点の規定について
①A種のように、降伏点の下限値だけが定められているのは、ごく普通のことです。普通は強ければ強いほど良いのですから。
②B種、C種が、降伏点(降伏強度)の上限値も定められている理由は、降伏比(降伏強度/引張強度)を大きくしないためです。
降伏比が小さいほど、降伏してから最大強度(=引張強度)までの余裕があり、塑性変形能力が大きくなりますからね。
■さて、SN400A、B、Cの降伏点の下限値(板厚40mm以下)はいくつですか?
→どれも235N/㎟です。〔構造No.25〕(SN400B・SD345の数値の意味)で確認しておきましょう。









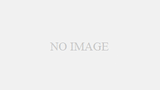
コメント