題名:「強度」と「たわみ・断面寸法」
過去問・類似問題
問題1 構造 R05-17
鉄骨造の建築物において、大スパンの梁部材に降伏点の高い鋼材を用いることは、鉛直荷重による梁の弾性たわみを小さくする効果がある。
問題1 誤
問題2 構造 R02-17
ラーメン架構の柱及び梁に、建築構造用圧延鋼材SN400Bを用いる代わりに同一断面のSN490Bを用いることで、弾性変形を小さくすることができる。
問題2 誤
・鋼材は強度を大きくしてもヤング係数は変わらないので、たわみは同じです。
問題3 構造 R03-17
曲げ剛性に余裕のあるラーメン架構の梁において、梁せいを小さくするために、建築構造用圧延鋼材SN400Bの代わりにSN490Bを用いた。
問題3 正。
強度を大きくすれば断面寸法(梁せい)を小さくすることができる。
覚え方・解説
強度を大きくすると
■たわみは小さくできない。
■断面寸法(梁せい)は小さくできる。
■たわみについて
・たわみは、例えば片持ち梁の先端に集中荷重が働く場合は、次の公式で求められます。
δ=PL^3/3EI
・したがって、たわみを小さくするためには、分母のE(ヤング係数=硬さ)を大きくするか、I(断面二次モーメント)を大きくする必要があります。
①ヤング係数E
・鋼材は強度を大きくしてもヤング係数Eは変わらないので、たわみは同じです。
②断面二次モーメントI
・断面二次モーメントIは、次の公式で求められます。断面二次モーメントIを大きくするためには断面寸法を大きくする必要があります。強度を大きくしても断面二次モーメントは変わりません。
δ=PL^3/3EI
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
■断面寸法(梁せい)について
・直感と異なるのは前述の「たわみ」のほうであって、「断面寸法(梁せい)」のほうは直感で十分理解できるはずです。
・一言で言えば、強度を大きくすれば、断面寸法(梁せい)が小さくても耐えられるということです。
・少し専門的に言えば、許容応力度設計では「応力度≦許容応力度」を満たすことが求められます。
・強度が大きければ、右辺の許容応力度が大きくなります。
・左辺の応力度は一言で言えば、「力/断面積」です。(曲げ応力度は「曲げモーメント/断面係数」(M/Z)です。)
・したがって、右辺の許容応力度が大きくなれば、左辺の分母の「断面積」は小さくできます。つまり、断面寸法(梁せい)を小さくできるのです。 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――









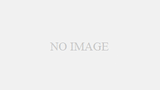
コメント